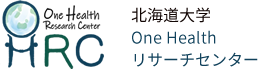【感染症発生情報】北海道初の重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:SFTS)
2025/8/30
北海道大学One Health Research Center(OHRC)は、国立感染症研究所などと共同でつくる動物SFTS検査ネットワークに参画しており、主に北海道における動物のSFTSの検査を実施しています。獣医師は、下記リンク中「動物感染症パネル依頼フォーム」の「ダニ媒介性感染症パネル」より依頼いただきますようお願いいたします。
https://ohrc.vetmed.hokudai.ac.jp/special-inspection/#about
1.北海道のSFTS事例
本年8月6日、北海道において1例目の重症熱血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:SFTS)患者が確認されました1。札幌市によれば、患者は道央圏在住の60歳代の男性で、発熱、頭痛、筋肉痛、下痢などの症状があるとのことです。また、感染地域は北海道内であり、感染経路は不明です。
7月下旬、患者がマダニに肩を咬まれていることに気づき、マダニを除去後、30日に上記の症状を示し、8月2日に医療機関を受診し、6日にSFTSウイルス検査陽性となりました2。
2.SFTS
1)原因
SFTSは、SFTSウイルス*により引きおこされるマダニ媒介性の新興感染症です3。ヒトは、主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺されることによりウイルスに感染するとともに、SFTSを発症している動物との接触により感染することがあります。
*SFTSウイルス:SFTSウイルスはフェヌイウイルス科(Phenuiviridae) バンダウイルス属(Bandavirus)に属し、ウイルス粒子は約110nmの球形、エンベロープを持ち、粒子内にウイルスタンパク質に覆われた3分節のマイナス鎖の一本鎖RNAをもっています。SFTSウイルスは酸や熱に弱く、一般的な消毒剤(70%エタノール、1%ビルコン、0.5%次亜塩素酸ナトリウム、消毒用アルコールなど)や、台所用洗剤、紫外線照射などで感染性がなくなります。また、乾燥状態では24時間以内に不活化します4、5。
なお、SFTSは感染症法では四類感染症、SFTSウイルスは三種病原体です6、7。
2)発生状況
(1)ヒト
2009年、SFTSは中国ではじめて発生が報告され、2011年に原因ウイルスが特定されました8。それ以降、東アジアや東南アジア(中国、韓国、台湾、ベトナム、タイ、ミャンマー)で患者が確認されています。
日本では、2013年以降、西日本を中心に患者が確認(後の検証により2005年に発生があったことが確認)され、近年は年間100件以上の発生報告があり、本年は、第32週時点(8月13日までの採材サンプル)で合計135件(第32週は8件)確認されています9、10、11
SFTSの発生は、媒介節足動物であるマダニの活動時期と一致し、5月をピークとし、10月頃まで続きます。ただし、冬季であってもマダニの活動は緩慢ながらも継続します5。日本でこれまでに確認されたSFTS患者の年齢層は、5歳~90歳代で、全患者の約90%が60歳以上です。亡くなった患者の多くは50歳以上で、高齢者は重症化しやすいと考えられています4、5。
(2)動物
動物におけるSFTSの調査は各国で行われており、患者の発生地域では野生動物の抗体保有率が高く、さまざまな動物種がSFTSウイルス感染に感受性であることが分かっています5。一般的に動物がSFTSウイルスに感染した場合、多くは症状を示さない(不顕性感染)と考えられていますが、ネコでは発熱、元気消失、嘔吐(おうと)、黄疸などの症状を示し、重症化して約6割が死亡しています。また、国内のシカ、イノシシなどの野生動物や猟犬の血液を検査したところ、SFTSウイルスに対する抗体を持つ個体がいることが分かっています4。
ネコとイヌにおけるSFTS発症数は年々増加しています。ネコについてはヒトの1.5倍の発症数が報告されています。イヌはネコの10分の1程度の発症数でした。発生地域は、ヒトの報告例と同様に、西日本の広い地域で確認されていますが、次第に東日本でも増加しています5。
飼育している動物の健康状態の変化に注意し、動物が体調不良の際には、マスク、手袋などを着用し、咬まれたり舐められたりしないように注意したうえで、動物病院で診てもらうようにしてください4。
3)症状
SFTSウイルスに感染した患者は、6日~2週間程度で突然の発熱、下痢や下血といった消化器症状、リンパ節腫脹、呼吸器不全症状、出血症状とともに血小板減少や白血球減少がみられ、重症例は出血傾向や意識障害を伴い、死亡することがあります4、12。致死率は約10~30%とされ、中国では10%超8 、13、日本では27%との報告があります14。
4)感染経路
日本では、マダニ(フタトゲチマダニとキチマダニなど)がヒトへの感染に関与しています10。
日本国内では、これまでに複数のマダニからSFTSウイルスの遺伝子が検出されています。SFTSウイルス保有率は地域や季節によりますが、0~数%です4。
ヒトは、主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺されることで感染します。SFTSを発症している動物との接触により感染することもあります12。感染動物の体液などを介した濃厚接触によってもウイルスが伝播する可能性があることから、特に動物との接触機会の多い獣医療関係者は注意が必要です5。
動物由来食品(肉や乳など)を食べたことによって、ヒトがSFTSウイルスに感染したという報告はありません。一般的な注意事項として、野生動物を食用にする場合(ジビエなど)は、動物由来感染症や食中毒を防ぐ観点から、捕獲・処理・加工する際の衛生的な処理や十分な加熱調理など、適切な取扱いが重要です4。
SFTSウイルスに感染したペットのネコやイヌとの接触により感染したと考えられる症例も報告されています。また、海外では患者の血液や分泌物との直接接触が原因と考えられるヒト間の感染の報告が以前からあり、2024年3月に国内で初めてのヒト間の感染事例(患者→医療従事者)が報告されました4。
5)診断
(1)ヒト
ヒトは、医療・検査機関などにおいて、血液、血清、咽頭拭い液、尿からウイルスやウイルス遺伝子の検出、血清から抗体を検出した結果をふまえて診断します12。
(2)動物
動物は、動物が体調不良の際には、獣医師や動物病院にご相談ください。OHRCなど動物SFTS検査ネットワークをはじめ、各地にSFTS検査を請け負う研究機関や試験機関があります。なお、動物については診断後に法令をふまえた特段の対応はありません5、15。
6)治療
ヒトおよび動物の治療は対症療法が主体となります。ヒトに関してこれまで日本で承認されたワクチンはなく、病状の進行が予期される場合には、抗ウイルス薬(ファピピラビル)の使用も検討されます5、9、12。
7)予防
(1)ヒト
動物に触ったら必ず手を洗いましょう。動物を飼育している場合、過剰な触れ合い(口移しでエサを与えたり、動物を布団に入れて寝るなど)は控えてください。ペットの健康状態の変化に注意し、ペットが体調不良の際には、マスク、手袋などを着用し、咬まれたり舐められたりしないように注意したうえで、獣医師や動物病院で診てもらって下さい。ペットがマダニに刺されないようダニ駆除剤も有効ですので獣医師にご相談ください。
野生動物は、どのような病原体を保有しているか分からないため、野生動物との接触は避けてください。また、動物の死体などに接触することは控えましょう。体調に異変を感じたら、早めに医療機関で診察を受けてください。受診する際は、ペットの飼育状況やペットの健康状態、また動物との接触状況についても医師に伝えてください4。
マダニは春から秋(4~10月)にかけて活動が活発になります。草むらなどマダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボンを着用し、サンダルのような肌を露出するようなものは履かないなど、マダニに刺されない予防措置を行うとともに、SFTSウイルスに感染した野生動物、ペット、患者の体液との接触を避けることが必要です。屋外活動後は入浴し、マダニに刺されていないか確認してください。特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部、髪の毛の中などがポイントです1、10。もし、吸血中のマダニが体に付いているのを見つけた場合、無理に引き抜こうとしないでください。また、マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱などの症状が認められた場合は医療機関で診察を受けてください。マダニに対する忌避剤(虫よけ剤)も市販されていますが、マダニの付着を完全に防ぐわけではありません1。
(2)動物
ワクチンはありません。マダニ駆除薬の使用、散歩前のマダニ忌避剤の塗布、散歩後のブラッシングを実施してください15。
(了)
〇参照資料
- 札幌市、ダニ媒介感染症:https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/f33madani.html
- 札幌市、重症熱性血小板症候群(SFTS)の発生について:https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/documents/20250807press_2.pdf
- 国立健康機器管理研究機構(JIHS)感染症情報提供サイト:https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/45/530/article/110/index.html
- 厚生労働省、SFTSに関するQ and A:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html
- JIHS、獣医療関係者のSFTS発症動物対策について(2025年バージョン2):https://www.niid.jihs.go.jp/content2/research_department/vet/animal-borne-2_2025-08-26.pdf
- JIHS、重症熱性血小板減少症候群(SFTS):https://www.niid.jihs.go.jp/content2/research_department/vet/animal-borne-2_2025-06-10.pdf
- 札幌市、マダニ対策、今できること:https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/documents/20250729-tick-prevention.pdf
- Yu XJ, et al. (2011) N Engl J Med 364:1523-32.
- 厚生労働省、SFTS診療の手引き(2024年度版):https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001229138.pdf
- JIHS、重症熱性血小板減少症候群(SFTS):https://id-info.jihs.go.jp/diseases/sa/sfts/index.html
- JIHS、Provisional cases of notifiable diseases by prefecture in Japan :https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/en/rapid/2025/32/zensu32.csv
- 厚生労働省、重症熱性血小板減症候群(SFTS):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html
- Xu B, et al. (2011) PLoS Pathog 7: e1002369
- Kobayashi Y, et al. (2020), Emerg Infect Dis 26: 692-699.
- 東京都獣医師会、人と動物の共通感染症ガイダンス、重症熱性血小板減少症候群:https://tvma.or.jp/activities/guidance/infections/sfts/
ご寄付のお願い donation
OHRCでは研究、教育活動に加え、学内連携、国際連携、産学連携、及び統合データベースの運用、特殊検査サービスの展開と多岐にわたる活動を行っています。これらの活動を支えるためのご寄付を是非お願い致します。
頂きました寄付金は大学からの交付金や外部資金では賄いにくい用途(例えば統合データベースの運用、特殊検査サービスの展開等)を中心に柔軟に活用させて頂きます。
※上記ページ(学部等支援事業)から申込みいただき、寄附目的欄に『獣医学研院One Health Research Center』とご入力ください。