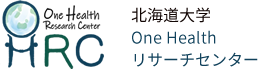【専門家からのレター】アザラシやラッコが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染したのはなぜ?
2025/7/11
 Healthリサーチセンターでは、野生動物などの大量死や不審死といった事案に緊急対応するチーム「HOT-WIRE: Hokkaido university One health Team for Wildlife Incidence REsponse」を立ち上げ、アカデミアの立場から科学的知見や診断技術を提供しています。
Healthリサーチセンターでは、野生動物などの大量死や不審死といった事案に緊急対応するチーム「HOT-WIRE: Hokkaido university One health Team for Wildlife Incidence REsponse」を立ち上げ、アカデミアの立場から科学的知見や診断技術を提供しています。
2025年4月18日には、根室市内でゼニガタアザラシが死亡しているとの知らせを受け、翌19日にHOT-WIREメンバー2名が現地に急行し、根室市歴史と自然の資料館および猛禽類医学研究所と協力して検体を採取しました。
それら検体について、北海道大学大学院獣医学研究院および人獣共通感染症国際共同研究所と合同で診断を実施した結果、ゼニガタアザラシ2頭から高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出しました。また、ゼニガタアザラシにつづき同地区で死亡したラッコについても、高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出し、北海道と環境省へ報告しました。
この記事では、アザラシやラッコの高病原性鳥インフルエンザ感染について専門家の考えを紹介します。今回、国際獣疫事務局 (World Organisation of Animal Health: WOAH)*1 の鳥インフルエンザ リファレンスラボラトリー*2長であり獣医学研究院長の迫田義博先生 (OHRC兼任教員) にお話を伺いました。
(インタビュー・文 One Healthリサーチセンター 大谷祐紀)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
鳥インフルエンザと聞くと、ニワトリ、殺処分、エッグショック、という単語が思い浮かぶ人も多いかもしれません。一方、今回はゼニガタアザラシやラッコという鳥でも家畜でもない動物の感染が報告されました。いわゆる家禽での感染と、今回報告されたような野生動物の感染について、どのように考えれば良いでしょうか?
最近よく耳にする高病原性鳥インフルエンザウイルスは、もともと病原性のないインフルエンザウイルスがニワトリなどの中で循環し続けることで、病原性の高いウイルスに変異したものと考えられています。
(インフルエンザウイルスの変異や世界への拡がりについてはこちらの記事で概説しています)
このウイルスだけでなく、インフルエンザウイルスは全般に、ウマやブタ、ヒトといった哺乳類に感染し、多くの場合は咳や発熱といった呼吸器症状を示します。一方、高病原性鳥インフルエンザウイルスの場合、感染力が強く、種によっては全身に症状が起こり、死に至ることがしばしばあります。その感染拡大を防ぐため、養鶏場のニワトリなどで感染が認められた場合、同じ鶏舎内のすべてのニワトリを殺処分することが法律で義務付けられ、2024-2025年度のシーズンでは約932万羽が殺処分されました。
(ニワトリと高病原性鳥インフルエンザの関係についてはこちらの記事で紹介しています)
高病原性鳥インフルエンザウイルスは野生の鳥とともに日本に運ばれてくると考えられています。野生動物の生息域と養鶏場や私たちの生活圏は、カラスや他の野鳥、そしてヒトの移動によりつながっているため、野生動物の感染とニワトリの感染はまったく別問題ではないと考えて良いと思います。
現在の事実として、根室地域の海鳥が高病原性鳥インフルエンザウイルスで多く死んでいると報告されていますので、今回の事例については、高病原性鳥インフルエンザウイルスが何かしらの要因で海鳥に拡がり、同じエリアに生息するアザラシやラッコが海鳥の糞や唾液などの分泌物、もしくは死体に接触することで感染したと考えています。
ニワトリなどの家禽で高病原性鳥インフルエンザ感染が疑われた場合、農家などの飼養者は家畜保健衛生所 (都道府県) に速やかに報告することが法律で義務付けられています。一方、今回のように野生動物の感染が疑われた場合、どのような組織が関与し、どのような流れで検査・診断が進むのでしょうか?また、感染が判明した場合、現場ではどのような対応が取られるのでしょうか?
家禽の高病原性鳥インフルエンザ感染の場合は農林水産省ですが、通常、野生動物では環境省が中心になって対応します。野生動物の感染は、一般の方が市役所などに通報することで発見されることがほとんどです。
鳥については環境省が詳細なマニュアルを整備しており、集団死などで高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が疑われる際には都道府県が死体を回収して簡易検査*3をします。簡易検査で陽性となると検査材料が国立環境研究所*4に送られて、詳細な検査が実施されることになります。通常、死体は焼却処分され、また死体の回収場所から半径10 km以内で他の野鳥が死んでいないか監視が強化されます。
一方、今回のように野生の哺乳動物で高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が疑われる際のマニュアルは十分に整備されておらず、調査や検査は大学等研究機関の自主的な努力のもと実施されています。また、死体の処理方法はまだ手探りで、これからマニュアルを整備しなくてはならない状況です。
国際的に哺乳動物の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染をどのように診断するかはまだ手探りな状況です。WOAHリファレンスラボラトリーとしてはこのような事例の診断実績を積み重ねることで、診断に適したサンプルの採取方法を検討しています。
アザラシなどの海獣が鳥インフルエンザウイルスに感染したという事例は海外では知られているのでしょうか?
アザラシ類の鳥インフルエンザウイルス感染の歴史は実は古く、1979年から1980年にかけて、米国マサチューセッツ州の海岸でゼニガタアザラシが鳥インフルエンザウイルス感染で大量死した記録があります。2021年以降に限っても、ヨーロッパや南北アメリカでは高病原性鳥インフルエンザウイルスがアザラシ類に感染したという報告があります。海鳥と非常に近い距離に住むアザラシ類は、海鳥のもつインフルエンザウイルスにも暴露される機会が多いのだと考えられます。
鳥類の感染症だったものが、哺乳類に感染した、ということで、私たち人への感染が少し近付いたと感じる人もいるかもしれません。今回の事例を受けて、人への感染について、私たちはどのように考えれば良いか、教えてください。
今回のアザラシも、海鳥の持つウイルスに大量に暴露されたことが感染の原因と考えられます。アザラシはもともと鳥類が持っているウイルスに感染しやすい(高い感受性を持つ)という特徴があるので、ウイルス自体がすべての哺乳動物に感染しやすくなっているわけではないと考えています。
ただし、人も大量のウイルスに暴露されれば鳥インフルエンザウイルスに感染するリスクがあります。鳥類やアザラシだけでなく、さまざまな野生動物の死体には鳥インフルエンザウイルスや、ほかの人獣共通感染症の原因となるウイルスが潜んでいる可能性があります。今回の事例を機に、野生動物の死体には不用意に触れない、多くの動物が死んでいたり、異常行動を示す動物がいる場合は行政に連絡する、もし死体を回収する場合は手袋などの保護具を着用し、その後は必ず手を洗うなど、私たちにもできる対策を徹底していただければと思います。
*1 国際獣疫事務局(WOAH):動物衛生及び人獣共通感染症に関する国際的な基準を策定する国際機関。
*2 WOAH リファレンスラボラトリー:動物疾病の診断及び診断方法に関する助言や診断に利用する標準株・診断試薬の保管などを行う、WOAH指定の研究機関。
*3 簡易検査:15分程度でウイルス感染の有無が診断できる検査方法。ただし、感度・精度ともに100%ではなく、偽陰性や偽陽性の可能性があることに注意が必要。通常、私たちが病院で受けるインフルエンザ検査と類似のもの。
*4 国立環境研究所:環境省所轄の環境問題に関する公的研究機関。野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルスの診断を通じて、生物多様性の保全に貢献している。
ご寄付のお願い donation
OHRCでは研究、教育活動に加え、学内連携、国際連携、産学連携、及び統合データベースの運用、特殊検査サービスの展開と多岐にわたる活動を行っています。これらの活動を支えるためのご寄付を是非お願い致します。
頂きました寄付金は大学からの交付金や外部資金では賄いにくい用途(例えば統合データベースの運用、特殊検査サービスの展開等)を中心に柔軟に活用させて頂きます。
※上記ページ(学部等支援事業)から申込みいただき、寄附目的欄に『獣医学研院One Health Research Center』とご入力ください。