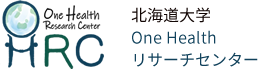【コラム】鳥インフルエンザの拡がり
2025/4/16
冬の訪れとともに、よく耳にするようになった「鳥インフルエンザ」。この感染症によって、何百万羽のニワトリが殺処分され、野生に生きる動物も人知れず命を落としています。この鳥インフルエンザ、どこからやってきたのか。その「はじまり」を見ていきます。
(One Healthリサーチセンター 日尾野隆大 大谷祐紀)

(イラスト TSUKIHI design 小野 遥)
一般に、ウイルスは環境に合わせて「変異」し、変異したウイルスはこれまで感染しなかった動物に感染するようになったり、その症状を変えるようになります。インフルエンザウイルスも、もともとは野生のカモなどの腸にいるウイルスにすべて起因しますが、変異を繰り返すことで、人や豚、馬など、さまざまな動物に感染するようになりました。
現在、鳥の間で流行している鳥インフルエンザウイルスは「H5亜型」という型に分類されます。カモ類にいたウイルスがニワトリに感染し、ニワトリ間で連続的に感染が続いた結果、1996年頃にニワトリにとって病原性の強いH5亜型ウイルスに変異しました。感染した鳥では、全身でウイルスが増殖し、呼吸器からの分泌物や羽毛、糞便など、体中からウイルスが排出され、まわりの鳥に感染を拡げます。
この鳥インフルエンザウイルスは偶発的に野鳥に感染します。そして、水辺を介すことで、多くの鳥に感染していきます。鳥の種類や個体によって症状が異なり、特にカモのような渡り鳥はウイルスを持っていても強い症状を出さないことが多いため、春と夏の渡りに伴って、鳥とウイルスが一緒に大陸間を移動しています。そうして毎年、日本にも鳥インフルエンザウイルスがやってきていると考えられています。
北海道大学がある北海道は多様な野生生物の生息地であり、残念ながらそれら動物の鳥インフルエンザ感染が報告されています。たとえば、オジロワシやオオワシなどの猛禽類や肉食のキツネはウイルスに感染した鳥を食べることで、このウイルスに感染します。また、トドやアザラシといった海棲哺乳類へのウイルス感染も南アメリカやロシアで報告されており、2025年4月には北海道でもゼニガタアザラシの感染が確認されました。
いわゆる自然環境と私たちの生活圏をつなぐ身近な動物にも、鳥インフルエンザの感染は拡がっています。人の生活圏に生息し、人間そのものや人が作ったものの恩恵を受けて生活する野生動物をシナントロープと呼び、カラスはその代表動物です。鳥インフルエンザが日本で流行する時期になるとカラスは「塒(ねぐら)」と呼ばれる群れを作るため、一度そこにウイルスが侵入すると、多くのカラスが感染します。死んだカラスの体内には、ほかの動物に感染を拡げることができる量のウイルスが残り、カラスを介して感染が拡がっている可能性が考えられています。特に、養鶏場の周りにカラスがいることも多く、ニワトリにウイルスが拡がる要因のひとつとして注意が払われています。
このように、自然の中で野生生物と共生していたウイルスが世界に拡がり、そして私たちの生活に入り込んできています。その理由は複合的でわかっていないことも多くありますが、人にも動物にも感染を拡げないために、私たちができることもあります。たとえば、水鳥が集まる場所に立ち入らない、立ち入った場合も靴や衣服を洗浄するなど、小さな努力によって防げる感染があります。ほかにも、鳥が集まる餌付けなどを控えることも大切です。
野生動物由来の感染症の拡大や、野生動物による農作物への食害、クマと人の軋轢など、近年、動物と人の距離感を考える機会が増えました。動物の生態や感染症について正しく理解することは、動物との適切な距離を考える上で重要です。私たちは大学という立場から、カラスを含む身近な野生動物の鳥インフルエンザウイルス感染を調査研究するとともに、科学に基づく情報を社会と共有することで、ニワトリやカラスを含むあらゆる動物、そして人の健康を守ることができると信じ、活動を続けています。
ご寄付のお願い donation
OHRCでは研究、教育活動に加え、学内連携、国際連携、産学連携、及び統合データベースの運用、特殊検査サービスの展開と多岐にわたる活動を行っています。これらの活動を支えるためのご寄付を是非お願い致します。
頂きました寄付金は大学からの交付金や外部資金では賄いにくい用途(例えば統合データベースの運用、特殊検査サービスの展開等)を中心に柔軟に活用させて頂きます。
※上記ページ(学部等支援事業)から申込みいただき、寄附目的欄に『獣医学研院One Health Research Center』とご入力ください。